— NISAインデックス全盛の日本で、なぜRL360(アクティブ運用)を“持つ価値”があるのか
インデックス投資(eMAXIS/オルカン等)の超低コストを基準にすると、RL360(オフショア積立)×アクティブファンドの費用は相対的に高く見えます。
だからこそ今日は、“手数料だけで判断しない”ための視点を、プロの運用設計の観点から整理します。
目次
結論(先に要点)
-
コアは低コストでOK:新NISAの長期・低コストインデックスは“基礎代謝”として最強。
-
でも、通貨分散・テーマ分散・リスク制御まで視野を広げると、RL360×良質なアクティブは“上乗せの筋肉”になり得る。
-
アクティブは**手数料でなく“実力(ネットの超過収益×下落耐性×アクセス”)**で評価すべき。RL360は世界中の優良アクティブにアクセスでき、外貨建てと継続設計(強制積立)という“器の価値”がある。
まず、誤解をほぐす:手数料は“コスト”でなく“戦略選択の価格”
-
インデックスは市場平均−極小コストを取りに行く戦略。期待は「市場並み」。
-
アクティブはコストを支払って“市場と違う”ポジションを狙う戦略。**期待は「市場平均を上回る/下落を浅くする」**のいずれか(もしくは両方)。
つまり、「コストが安い=常に正解」ではない。
**“そのコストで何を買っているか?”**が本質です。
RL360(アクティブ)で“何が買える”のか
1) 通貨の第二エンジン(USD/EUR等)
-
円だけに依存しない。ドル建ての資産形成は、長期の円安局面で**“自然な上乗せ”**になり得る。
-
国内証券では扱いが限られる外貨建てアクティブにも、小口で積立できる。
2) 日本のNISAでは買いにくい世界のアクティブ
-
例:米大型グロース、世界品質株、AI・医療革新、新興国中小型、戦略債券、オルタナ風味の絶対収益型など。
-
ボラ下げのディフェンシブ運用(配当成長・クオリティ重視)や、ベータを抑えた債券/クレジット戦略で、下落耐性を厚くできる。
3) 継続・強制力という設計(ここが地味に大きい)
-
毎月自動で外貨建てを買い続ける“仕組み”そのものが価値。
-
人間は下げ相場でやめたくなる。やめない設計が長期成績の第一因子です。
“費用の高さ”をどう見る? —— ネットの実力で評価する
アクティブ評価の3点セット
-
ネットリターン(=グロス−手数料):同カテゴリ・同リスクで5〜10年比較
-
最大ドローダウン/回復速度:崩れにくさは複利の味方
-
相関と役割:既存のインデックスと**“違う動き”**をするか(分散効果)
単に“信託報酬が高い/安い”ではなく、**手数料を払った“後”に何が残るか(ネットの超過収益・下落耐性・相関低下)**で判断。
具体イメージ:手数料×超過収益の“残差”で考える
-
前提:
-
インデックス(低コスト):**年率6.0%**想定
-
アクティブ(総経費高い):**グロス7.5% − 手数料1.5% = ネット6.0%**なら“同点”。
-
しかし下落相場で−30%を−22%に抑える(ディフェンス)なら、回復速度で最終リターンは上振れし得る。
-
逆に強気相場で上回る(テーマの当たり)ならネットで+αが残る。
-
勝ち筋は2つ:
① 下げを浅くする(複利を壊さない)
② 当たりテーマで上振れ(ネットの超過収益)
これが**“費用の対価”**です。
「高いか安いか」より「役割が重なるか」をチェック
-
既にNISAでオルカン×S&Pを厚めに持っている人が、同じベータのアクティブを足しても効果は薄い。
-
RL360では、為替・資産・スタイルが**既存コアと“かぶらない”**アクティブを選ぶのがコツ。
-
例:配当成長/クオリティ株、分散債券/インカム、低相関のオルタ系、**地域の穴埋め(インド/東南アジア)**など。
-
よくある誤解と回答
Q:インデックスより手数料が高い=負けでは?
A:**“コスト<機能価値”**なら勝ち。ネットで超過収益を出すか、下落を浅くするか、通貨&分散の役割を果たせているかで評価。
Q:アクティブは当たり外れが怖い
A:単品に賭けない。複数戦略に分散、年1回の見直し、継続前提の積立で“外れ”の影響を薄める。
Q:RL360は手数料や早期解約が不安
A:最初に“やめない額”で設計し、保有前提を20年に置く。初期コスト/管理費/ファンド費用は見積書で可視化。短期解約は不利を前提に“続けられる現実的な額”にする。
使い分けの結論(コア&サテライト)
-
コア(国内):新NISAの低コスト・広域インデックス=土台
-
サテライト(海外):RL360で外貨×アクティブ(通貨/資産/スタイルの“かぶり”回避)
-
運用ルール:
-
積立は止めない(やめると費用だけ残る)
-
年1回だけ配分点検(売買過多は厳禁)
-
サテライトが勝った年の一部利益をコアへ還流(“残す仕組み”)
-
まとめ:
-
インデックス=最強の基礎、アクティブ=戦略的な上乗せ。
-
RL360は、通貨分散×世界のアクティブ×継続設計という**“器の価値”**を提供する。
-
判断軸は手数料の多寡ではなく、ネットで何が残るか+分散効果+継続可能性。
-
NISA(基礎)×RL360(上乗せ)の二刀流は、“安いだけ”でも“高いだけ”でも届かない総合点を目指せます。
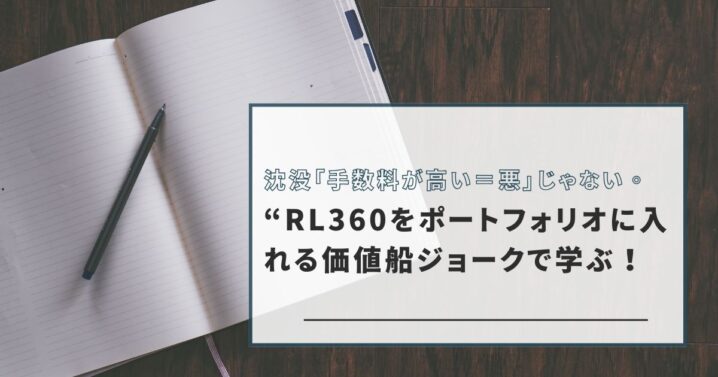

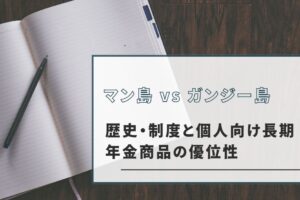
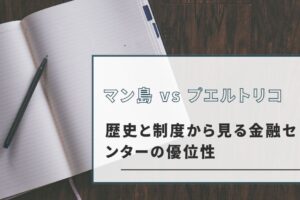

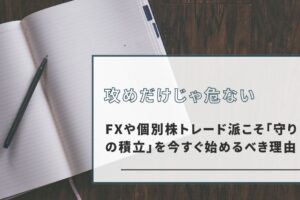



コメントを残す